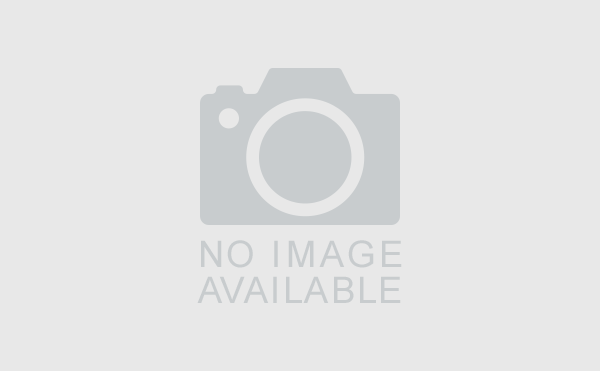面会交流の取り決めは必要?
公正証書に入れておきたい
2つの安心条項
離婚後に揉めやすい
「見落としポイント」
離婚を決めたとき、多くの人がまず考えるのは「養育費」や「財産分与」といったお金のこと。でも、実際に離婚後に多く寄せられる相談は、もっと日常に根ざしたトラブルです。
今回ご紹介するのは、公正証書に記載しておきたい「2つの安心条項」――それが【面会交流の取り決め】と【連絡先通知の義務】です。それぞれの中に、より細かな取り決め項目がありますが、どちらも離婚後のトラブルを防ぐために欠かせません。
たとえば…
- 面会の予定を一方的に変えられた
- 子どもの様子を知りたいのに連絡が取れない
- 病気や進学のことを伝えたくても無視される
こうした問題を防ぐには、離婚時にしっかりと「ルール」を決めておくことが大切です。
今回は、「面会交流の取り決め」と「連絡先通知の義務」について、公正証書に記載しておくべき理由をわかりやすくお伝えします。
面会交流の条項を
入れるべき理由
親権がない側の親であっても、子どもと交流を持つことは法律上の権利です。しかし、離婚に至った背景には感情的な対立があることも多く、「もう会わせたくない」と一方的に拒まれてしまうケースもあります。
また、親の都合で予定が変わったり、突然会えなくなったりするのは、子どもの心に大きな影響を与えます。
だからこそ、面会交流について書面でしっかり取り決めておくことが、親にとっても、そして何より子どものためにも大切なのです。
面会交流の内容は、
できるだけ具体的に
トラブルを防ぐには、「できるだけ具体的に決めておく」ことが大切です。
たとえば、以下のような内容を盛り込むと、あとからの行き違いが防げます。
具体的に決めておくと良い項目
こうした項目をあらかじめ決めておくことで、後からのトラブルやすれ違いを防ぐことができます。
- 面会の頻度(例:月1回、第2土曜日 10時〜17時など)
- 宿泊を伴うかどうか(例:長期休暇中は1泊まで可 など)
- 面会場所や引き渡し方法(例:親の自宅、公共施設など)
- 送り迎えの負担(例:原則として親権のない親が迎えに行く)
- 遠距離の場合の対応(例:住居の中間地点で引き渡す)
- 子どもの体調や気持ちへの配慮(例:本人の意向を尊重)
- 特別な事情がある場合の調整方法(例:事前に協議して決定)
こうした取り決めは、子どもにとっても安心感につながります。
また、親同士のやり取りも減り、感情的な衝突を避けやすくなります。
親権者側への配慮も忘れずに
面会交流の取り決めは、親権のない側の「会いたい気持ち」を尊重するだけでなく、親権者側の「生活のリズムを守りたい」「頻度が多すぎて困る」「子どもが嫌がっている」といった声にも配慮が必要です。
だからこそ、双方が納得できる形で、現実的なルールを設定しておくことが重要です。
おすすめ文言(例)
以下は、公正証書に記載する際の例文です。あくまで一例ですが、参考になります。
上記未成年者の意思を尊重し、事前に甲乙の協議により、その日時、場所及び方法を定め、未成年者の福祉に適うよう円満に実施するものとする。
面会交流は、原則として月1回、第2土曜日に甲が乙の自宅へ子を迎えに行き、同日17時までに乙のもとへ送り届けるものとする。
長期休暇中は、双方協議の上、宿泊を伴う面会も認める。双方の住居が遠距離にある場合は、中間地点で引き渡すこととする。
このように、子ども中心の視点と現実的なルールの両方を盛り込むことで、親も子どもも安心して関係を続けることができます。
連絡先の通知義務は
なぜ必要?
離婚後、時間の経過とともに引っ越しや転職で連絡先が変わることは珍しくありません。でも、連絡先を知らせてくれないままでは…
- 養育費が滞っても請求が困難になる可能性
- 面会の予定が立てられない
- 子どもの体調や進学に関する相談ができない
という問題が起きてしまいます。
「もう夫婦ではないから、連絡したくない」という気持ちもわかります。
でも、親としての役割を果たすためには、最低限の連絡体制は保っておくことが大切です。
以下は、公正証書に記載する際の例文です。あくまで一例ですが、参考になります。
甲と乙は、離婚の後、前記養育費の支払が終了するまでの間は、互いに住所、電話(携帯電話を含む)番号、勤務先(住所及び電話番号)に変更があったときは、速やかにこれを相手方に連絡し、告知しなければならないものとする。
※この文例はあくまで参考です。ご家庭の状況に応じて短くしたり、調整することも可能です。無理なく現実的に実施できる内容にしましょう。
書類にしておくことの
意味
面会交流や連絡先の義務は、口約束で済ませる人もいます。
ですが、離婚後の関係はどうしても不安定になりがちで、ちょっとしたことで約束が反故にされることも。
書面化しておくことで…
- お互いに冷静に判断できる
- 将来、子どもが大きくなったときの「記録」として残せる
- 法的にも主張しやすくなる
といったメリットがあります。親権を持っている側も、持っていない側も、子どもとの関係は一生続いていくもの。夫婦ではなくなっても、親としての責任と信頼関係は守っていきたいものです。
まとめ|子どもの未来を守るために今できること
面会交流や連絡先通知の取り決めは、離婚後の平和な関係のためにこそ必要です。感情が落ち着いている「今」だからこそ、冷静に取り決められることもあります。
子どもが安心して育っていけるように。
親同士の不要な衝突を防ぐために。
公正証書にしてルールを残しておくことは、未来の家族への「思いやり」です。